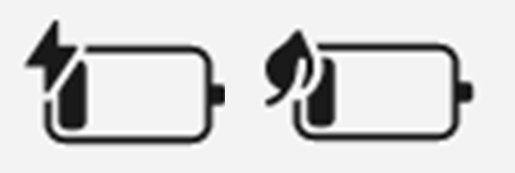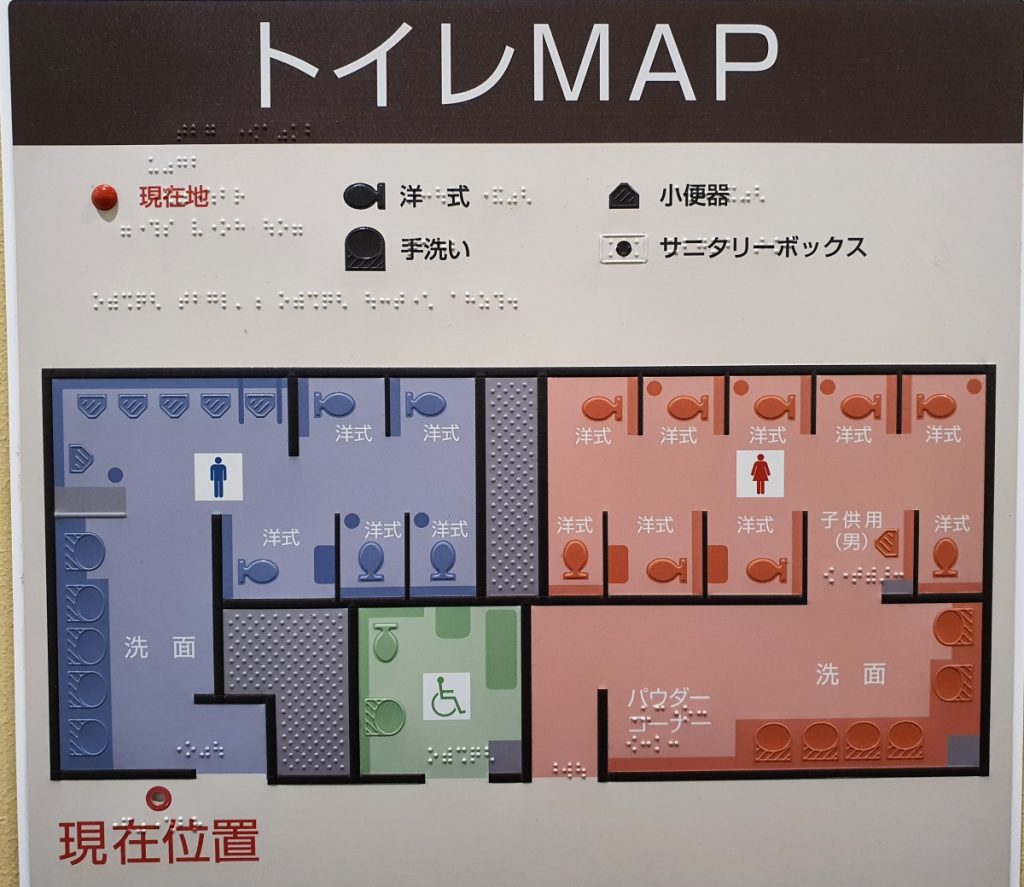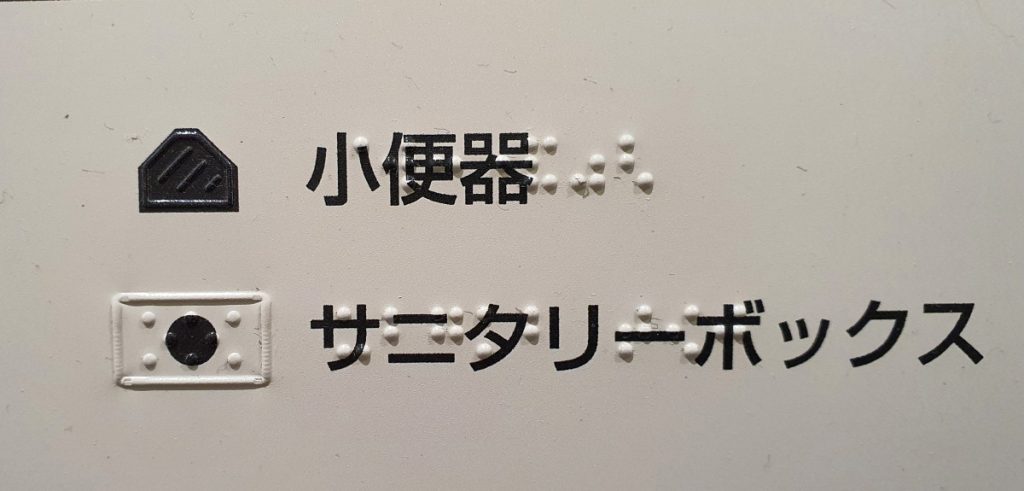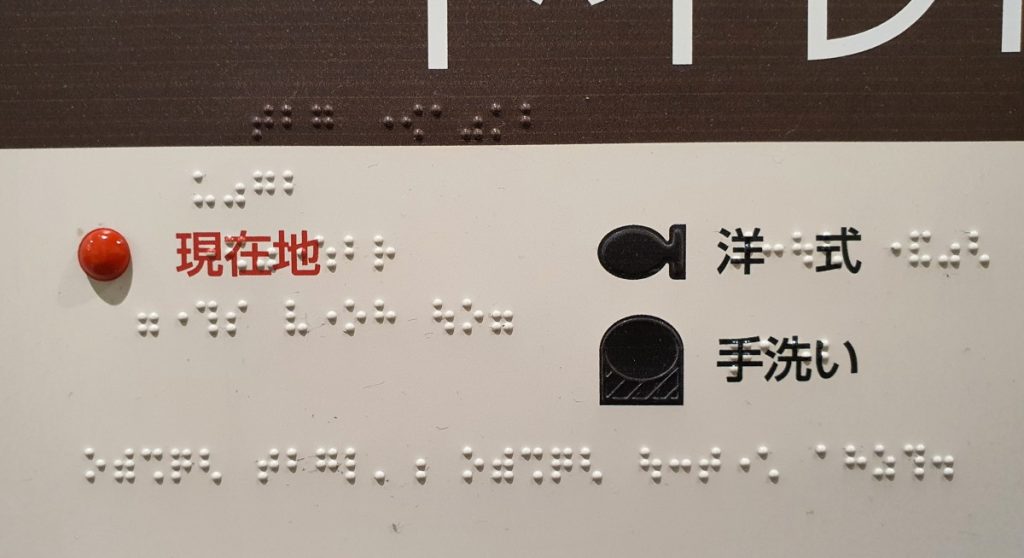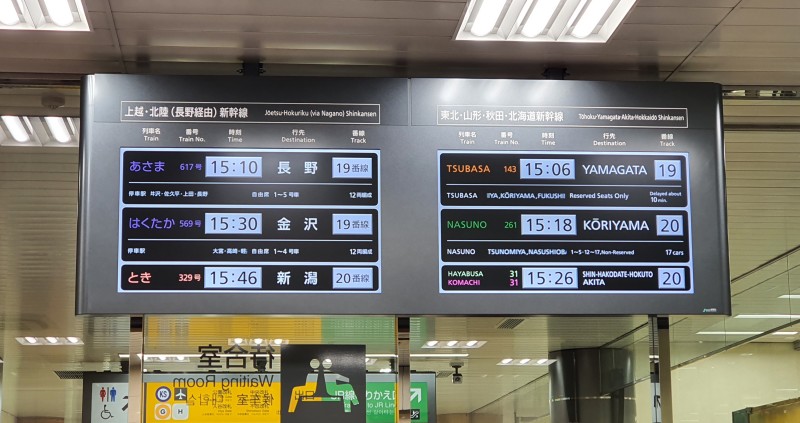7 月15日(土)から17日(月・祝)までの二泊三日、本学にて科学へジャンプ・サマーキャンプ2023が開催されました。今回は15周年&10回目のアニバーサリー回でした。それが理由というわけでもないのですが、この機会に少し昔話を記録しておこうと思います。
思い起こせば2008年に、最初の同イベントを戸山サンライズで実施したのが15年前です。欧州のサマーキャンプICCの経験を活かせないか、と鈴木昌和先生、山口雄仁先生、渡辺哲也先生、故藤芳衛先生らから誘われ、主要メンバーに加えて頂きました。
その後2009~2011年の3年間、JSTの予算がつきました。この頃は各盲学校さんとのネットワークを強化したり、地域版がスタートしたり、じわじわと活動を広めて行った時期です。この期間の全国対象のキャンプは2010年と11年の2回でした。
そしてJSTの支援が終わった翌2012年に守谷で実施した後、さすがに毎年はスタッフが疲れてしまうな…と気づきました(ようやく…)。そこで2013はサマーキャンプを実施しない代わりにICCHPへの参加支援のみ行いました。1年お休みです。その後、2014年に第5回のキャンプを同じ守谷で実施しました。
しかし、主要メンバーの先生方が関わる国際会議のICCHPも偶数年開催のため、偶数年の夏は本当に忙しい…。そういった理由から、2015年から「奇数年での開催」とすることにしました。そして無事、2017年、2019年と連続3回、「あいち健康プラザホテル」で実施したというわけです。この頃利用した同施設は、駅からは遠いものの全てまとまっているので、視覚障害の中高生を集めるには非常に適した場所でした。
実は2022まで、とにかく会場の選定が大変だったのです。宿泊場所は4~5名が一部屋で泊まれるところ、さらにワークショップを行う会議室が近くて、食事もできて…。なかなか条件に合致する「安い」施設はありません。通常のセミナーハウスはだいたい宿泊がシングルですし、食事もビュッフェスタイルが多いのです。視覚障害の中高生を集めるにはあまり適していません。青少年自然の家のようなところは2010年に使っているのですが、他の団体との調整がかなり煩雑で入浴時間が当日まで決まらないなど、やはり困難が多かったのです。
そんな状況でしたので、「ホテルのツイン、歩いて移動」はある意味トライアルでした。しかしその結果、「意外と良いのでは」というのが実施してみての感想でした。従来の半分程度の人数でしたが、それ故参加した生徒たちは、全員の声と名前などを認識してくれたように思います。1泊2日ではありましたが、我々の方も全員の名前と顔を覚えることができました。
このように進めてきた科学へジャンプ・サマーキャンプですが、コロナのために残念ながら2021は実施できませんでした。しかしこのままズルズルとやらないでおくと皆さんから忘れられてしまう…という危機感があり、2022年の9月に「1泊で10名」という形式で実施することにしました。従来の1/3の期間、半分の人数です。既に「サマー」ではないような気もしますが、まぁ大学はまだ夏休みだから…などと言い訳をしつつ、場所は渡辺先生のお膝元、新潟となりました。さらにこの年は「ホテルで泊まって会場に移動」というスタイルを試してみました。
というわけで2023です。当初夏休みの実施を予定していましたが、私の都合がつかず、7月の連休を利用することにしました。ほぼ2週に一回程度、何度もオンラインでの委員会を重ね、エクスカーションとしてJAXAを訪れることになりました。そして富山の地域版、科学へジャンプ・イン北陸に参加しているインテックさんに協賛&ワークショップを担当して頂いたり、とても充実したイベントになりました。
詳細は後日報告書としてアップしたいと思っていますが、15周年・10回目という節目に本学で開催できたことはとても嬉しく感じています。
卒業生もボランティアで駆け付けてくれましたし、在校生も協力してくれました。小規模なイベントではありますが、無事執り行うことができたこと、ご協力いただいた皆様のお陰です。感謝いたします。
2008年当初、「何の実績もない団体が募集しても、応募してくれる生徒さんがいるかどうか…」と心配していた科学へジャンプ。今では「科学へ」と検索ボックスに入れると「ジャンプ」まで補完してくれるようになりました。本当に驚きです。今後も、なんとか細く長く続けていけたらなぁと願っております。
(検索ボックスの件、自分の環境だけなのかな…と疑う時もあるのですが、そうでもないです….よね?)