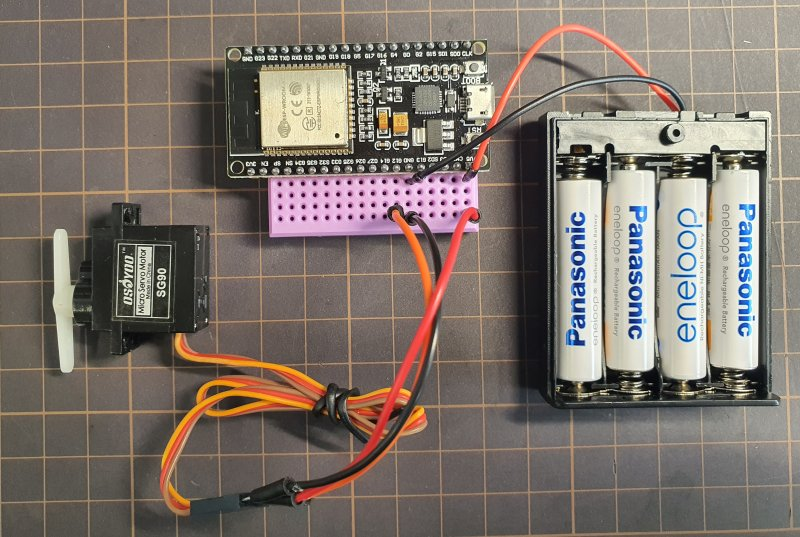この夏はJSPSの短期海外研究者招へい事業にてインドのマドラス・クリスチャン・カレッジからRobinson Thambraj博士をお迎えしています。日々山のようにノートにアイディアを書き溜めているRobinは会うたびに新しいアイディアについて話してくれます。
もちろん研究の話題以外に雑談もするのですが、先日「インドではikigaiが流行っている」と聞いて「?」となりました。「ikigaiですよikigai!」と言われて「生き甲斐」のことだと分かり、検索してびっくり。なるほど2015年ごろから日本の「生き甲斐」の概念は世界に広がっているのですね…
画像検索結果には、what you love / what you are good at / what the world needs / what you can be paid for の4つの円が描かれた図が並びます。 love / good atの重なるところにはpassion、love / the world needsの重なるところにはmission、the world needs / you can be paid forの重なるところにはvocation、you can be paid for / good atの重なるところにはprofession、そして4つの円が重なる場所に「ikigai」となっています。
ikigai diagramやpurpose diagramなどと呼ばれるこの図を含めて、ikigaiがそんなに注目されているとは恥ずかしながら初めて知りました。普段分かって使っているつもりの単語はわざわざ検索しませんものね…
https://www.bbc.com/worklife/article/20170807-ikigai-a-japanese-concept-to-improve-work-and-life
まるっきりこの話題とは関係ありませんがRobin曰く「日本の空の青は濃い。赤道直下のインドとは発色が違う」そうです。「雲の形や影も違うんですよ」とインドっぽい英語でつぶやきながらパシャパシャスマホで空の写真を撮っていました。